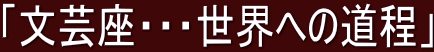
平田 純
アイルランドへの道
1976年のいつ頃だったろうか。9月からアメリカとイギリスへ2ケ月間文部省の短期留学に出かけることになって、アメリカの受け入れ先は決まつたが、イギリスはぜひ師事しかと思っていたオックスフォード大学のS・ウルマン教授が年初めに亡くなられて、別の大学と接触を取っていた最中だった。研究室の電話が鳴って、旧友の吉崎四郎さんの声が聞こえた。「僕が力を入れている劇団があって、連中がアイルランドへ行こうと言って準備中なんだ。これまで手紙を見ていたんだけど、忙しくなったので、君少し手助けしてくれないか」という趣旨の話だった。物珍しいことは直ぐに覗いて見たくなる性分はいつまでたっても変わらないもので、早速見せてもらうことにした。アイルランドのダンドークという町はタバコ産業などが盛んらしく、そういった産業界の人たちがスポンサーになって、エメラルド・グリーンの島で春5月に、国際アマチュア演劇祭が行われているのだ。吉崎さんの力を入れていると言っていた劇団が「文芸座」であった。
何度か手紙をやりとりする手伝いをした後、私はアメリカに出かけていった。それはアメリカが建国200年を祝い、カナダのモントリオールでオリンピック・ゲームが開かれた年であり、昭和天皇と皇后がデイズニーランドを訪れて、すっかり人気者になられた年であった。その賑わいか幾らか収まった9月末、私はオハイオ州の小さなアンティオーク・カレッジをはじめ、オバーリン・カレッジでクラスに出て、久しぶりの学生気分を味わつていた。巷ではフォード大統領とジョージア州知事ジミー・カーターの選挙戦が話題を集めていた。オハイオ州のシンシナテイ・レッズがワールド・シリーズの覇者に収まったことも、新聞記事をにぎわしていた。11月の初め頃、フイラデルフイアを発ってロンドンに着いていてみると、カーター当選のニュースが流れていた。アメリカは田舎町を旅してきたので、ロンドン大学のウニヴァシティ・カレッジではランドルフ・クワーク教授の許しを得て、ロンドンの実地見学に出ることにした。先輩留学生を紹介されて、ロンドン文学散歩的に各地を歩いて、時間的・空間的な見地からの調査を行った。これは後で作品を読むとき、非常に役に立ったと思っている。
期限が釆て11月の末に富山に帰ってくると、ダンドークと文芸座間の連絡が待っていた。いよいよ大詰めで具体的になり、セットの図面、色、大きさ、形、材料などの情報を送らねばならないのだ。こちらは、舞台のことも、用語も分からない。図面のことも分からかない。分からない尽くしで手を挙げてしまいそうになって、ふと一言洩らしてしまった。「一つミニチュアのセットを作って、色をかけて、それを見せるのが一番ですよ。」1月の半ばに、「夕鶴」と「三年寝太郎」の素晴らしいセットの模型を持ってダンドークに出かけた代表の小泉さんは、セットを手にして説明している小泉さんの写真が載っている新聞と向こうの連中が驚嘆していた話をお土産に帰国された。
来た、見た、勝った
「君たちは来た。僕たちは見た。君たちは勝った。」例のシーザーの「来た、見た、勝った」をもじったアラン・ニコル氏の批評が雄弁に物語っている通り、文芸座が演じた民話劇「夕鶴」と「三年寝太郎」の舞台はダンドークの観客を魅了し、演劇祭の最高賞を勝ち得たのであった。これは文芸座にとって、まさしくエポック・メーキングな出来事であったと言わねばならない。それまで、富山で主として「山村巡回公演」など地道な演劇活動を続けてきた人たちが、世界各国から集まっている観客、それも演劇関係の「日の肥えた」人たちの前で演じた舞台、しかも言葉が通じないというハンディキャップを背負いながら演じた舞台が、他のすべての参加者を圧倒して最高賞を得たのである。それは日頃の劇団活動が最高に評価されたことを意味するのだ。そこから得られる自信に加えて、「この土地で、演劇を通した知人友人を沢山作ることができたという目に見えない宝が得られたのである。とりわけ、アメリカから来ていたモート・クラーク教授との関係は、文芸座の世界への道を開いていくのに非常に重要であった。
アメリカヘの道
モート・クラーク教授がウエストチェスター・コミュニテイ・カレッジで開催されるウエストチェスター演劇祭に文芸座を招待したのは1981年であった。ニューヨーク州ヴァルハラで挙行されるこの演劇察では、文芸座はチェホフの「結婚の申し込み」とイヨネスコの「授業」を公演した。ダンドークでは土のにおいのする民話劇を舞台に乗せ、今度はアメリカで、翻訳劇の新しい実験的な作品と古典的な作品を公演したのである。ある意味では大胆なと思えるが、それは逆にこの劇団の自信のほどを披瀝したに過ぎないとも言えよう。真剣な「芝居道」に打ち込んできた劇団員の精進がもたらした余裕とも言うべきか。偶然は続きだすときりがない、というのは織田作之助の名言だが、ここでも、「結婚の申し込み」を取り上げたことが新しい繋がりを生み出してきた。
 ハンガリーの東部にあるデブレツェンから参加していたスタジオ・プレイヤーズというグループが同じ「結婚の申し込み」を演じたのだ。文芸座は日本風にアレンジされた演出で、畳に座って演ずるのに、ハンガリー・グループは椅子に腰掛けて舞台が展開する。まさしく東西文化の比較的考察にもってこいの場となった。「この二つのグループは一緒になって世界各地を巡業公演すべきである」と劇評家の1人が言っていたが、おそらくそれは実感であったろう。それほどまでに見る人の興味をかき立てたのだ。両グループは相手の舞台に開心を持ち、互いに相手の優れた点を見抜いたようだ。向こうの代表ピンツェシュ・イシュトヴァーン氏と小泉さんとの間に芽生えた尊敬と友情は、今後さらなる発展へと通じていった。
ハンガリーの東部にあるデブレツェンから参加していたスタジオ・プレイヤーズというグループが同じ「結婚の申し込み」を演じたのだ。文芸座は日本風にアレンジされた演出で、畳に座って演ずるのに、ハンガリー・グループは椅子に腰掛けて舞台が展開する。まさしく東西文化の比較的考察にもってこいの場となった。「この二つのグループは一緒になって世界各地を巡業公演すべきである」と劇評家の1人が言っていたが、おそらくそれは実感であったろう。それほどまでに見る人の興味をかき立てたのだ。両グループは相手の舞台に開心を持ち、互いに相手の優れた点を見抜いたようだ。向こうの代表ピンツェシュ・イシュトヴァーン氏と小泉さんとの間に芽生えた尊敬と友情は、今後さらなる発展へと通じていった。
八ンガリーヘの道ーカツィンクバルチカー
ハンガリーの北東部カツィンクバルチカという町で、若くして逝った優れた演劇人ホルバート・イシュトヴァーンを偲んで開かれる演劇祭がある。1982年6月末、文芸座はこの演劇察に招かれた。文芸座の皆さん一行7名に、通訳係として私が同行した。フランクフルト・アム・マインで乗り継いで、ようやく降り立ったブダペストのへリフェジ空港では、緑色の軍服に銃を持った兵士の巡回する姿が目に付いた。迎えに来た連中の小さな車に乗り込んで、一路かカツィンクバルチカへと暮れかかった道をひた走った。時折集落を通り抜けるのだが、その間は刈り取りを待つ熟した麦畑がひとしきり続き、その次は小さな花を付けたヒマワリ畑が続いて、畑と畑の間を仕切る木立が見えるだけ。教会の高い塔が見えてくると、そこに集落があるが、どうしたのか、人の姿は見えなかった。一度だけ、道ばたで黒い服を着込んだ老婦人が2人、何やら話し込んでいるのを見受けただけであつた。初夏の空は暮れそうでなかなか暮れなかった。広がった畑のずっと向こうに低い丘がばんやりと見えていた。そして、とっぶりと暗くなってやっと目的地に着いたのだが、会場の建物からは騒音としか聞こえない大きな音でジャズが流れていた。鉄のカーテンの向こうで迎える最初の夜であった。
日本式に言えば青少年の家といったような宿舎に入って一夜を過ごした。翌朝目覚めると窓の外に小鳥のさえずりが聞こえた。開いた窓からは暖かみのある土のにおいが入ってくる。ここは日本とは違ったところだ、ハンガリーなんだという実感がした。朝食のテーブルには小さくて堅く焼いたパン、テーといわれる蜂蜜入りのお茶、バター、ソーセージ、ハム、ピーマン、トマトなどが少量並んでいた。シャワー室に行くと、それぞれの仕切りに、太いパイプが頭の上にあって、パルプをひねると勢いよく水がほとばしり出てきた。調節が出来るとお湯も出るらしいが、どれもうまくいかなかった。それでも、係りの連中は心を込めて応対してくれているのが分かる。通訳担当をしてくれたエバさんはこの町の大工場に勤めるOLで、ブダペスト大学では経済学を専攻したという。近くの古い都ミシュコルツに案内してやろうと、どこからか車を用意してくれたほどまでに、彼女はこまめに気を使ってくれた。(車はすべて東ドイツ製で、ガソリンは輸入品で、すべてが完全にコントロールされている状況の中で、車を用意してまで案内してやろうというのは、並々ならないことであった。)
モート・クラーク教授やピンツェシュ氏との再会があり、色んな国から来ている連中と宿舎で、食堂で一緒になることから、国際的会合の雰囲気が高まってくる。単に芝居を見るだけでなく、こういった付き合いが何とも言えないくらい楽しい。文芸座の芝居、「結婚の申し込み」は無事終了。夜、当日行われた芝居について批評合が行われるので、それが気がかりであった。現に前夜公演したグループの1つが相当酷評されたという知らせが入っていた。
劇場の隣にある集会所の講堂に入ると、すでに満員であった。ブダペストの放送局員だという人が司会で文芸座の批評会が始まった。ハンガリー語でのやりとりを、彼が英語にしてくれる。それを私が日本語にして伝え、それに小泉さんが応答する。それを英語にして、またハンガリー語にする。そんな操作の繰り返しなので、時間がかかる。まして、演劇の専門用語が入るとひっかかる所が出てくる。まだるっこしいやりとりから、先ず聞きとれたのは、賞賛の言葉であった。彼らがこの劇のメッセージをよく理解していたことが窺えた。それから日本の演劇についての質問が出たりして、どれほどの時間を過ごしたのであったろうか、多分1時間半から2時間ほどで、劇評会は終わった。この劇評会に参加した人たちに好印象を与えたことは明かで、ほっとする思いであった。外に出たとき、快い疲れを覚えて見上げた夜空の星が美しかった。
−デブレツェンー
カツィンクバルチカからデブレツェンまで、私たちを乗せたバンは平坦な道を快調に走った。道の両側に高い並木が列をなして続いている。時折、藁を盛り上げて運んでいく馬車とすれ違う。いかにも牧歌的な風景だ。高い木の上に小技など積み重ねた鳥の巣を見つける。あれはコウノトリの巣だと教えられた。ほとんど変わらない風景の単調さは眠気を誘う。そうこうするうちに、目的地デブレツェンに到着した。ハンガリー第2の都市というが、くすんだ印象は否めない。ここは、第2次世界大戦の末期に、ハンガリー政府が移ってきて、議会が開催されたという歴史を持つところであり、新教のカルビィン派の総本山のあるところでもある。不死鳥をシンボルマークとしている。ここでも「結婚の申し込み」を公演し、神谷不二子さんの舞踊を披露して拍手喝采、大歓迎を受けた。別れの前夜、食事を終えて宿へ帰る道で、静けさを切り裂くジェット機の轟音を開いた。ブルガリアに駐在するソ連機が警備のために飛んでいるんですよと、髭のタマシュ氏がそっと教えてくれた。
あるエピソード
デブレツェンからは、汽車でブダペストに出て、ドナウの真珠といわれている町を見、ウィーンに立ち寄って帰国することになっていた。大小の道具類を送り返すために小泉さんと私は大きなトラックをチャーターしてへリフェージ空港に行かねばならなかったので、みんなのトランクも併せて積み込んで別行動をすることになった。とにかく、ブダペスト南駅でウィーン行き列車の発車時刻に会うことを約束して、朝の7時、トラックが先ず出発した。小雨が降り出して、古いトラックの運転席にはどこからか水が入ってくる。運ちゃんの肘をつついて飲むまねをすると、にやっと笑って、名も知らぬ町の、喫茶店に入ってくれた。
12時過ぎブダペスト空港に着いた時は雨は上がっていた。道具類も無事送り終えて、みんなと約束した駅まで連れて行ってもらった。トランクを下ろすと、約束のお金を受け取って、トラックの彼はいま来た道を引っ返していった。手押し事にトランクを積み込んで、さてウィーン行きの列車の出るはずのフォームを探しておこうと時間表を見たが、4時過ぎに出ると聞かされていた列車は見あたらない。変だと思って、赤帽さんに尋ねてみたが、彼は英語はだめだという。40年前に習ったドイツ語はこちらの方が忘れてしまっている。でも、その列車はここではなしに、別の駅から出ると言ってるらしい。インフォーメィションで聞いてみるとその通り、我々が乗るつもりのウィーン行き列車は東駅から出ることが確認された。トランクを積み上げた手押し車に寄りかかって、私は小泉さんにそのことを話し、これじゃ今日中にウィーンに着くことは出来ませんねと言った。先に着いて、ブダペストの町の観光に出ているみんなは駅が間違っていることを知らないで、時間近くになって来るのだから、それから発車駅までどんなに急いでも間に合わないと、思ったからだ。だが、小泉さんから戻ってきた返事に私はびっくりした。「そんならきっと連中はこの駅のどこかにいるはずです。そんなときにみんながどうするかは分かってます。この駅にいますよ。」そして二度びっくりしたことに、みんながいたのだ。駅の待合室で待っているみんなの姿を見たとき、私には奇跡としか思えなかった。同時に文芸座の人たちの結束・連帯・信頼ぶりに感動すら覚えた。これは大変なグループだというのが、偽り無い印象だった。
TIATFへの道
両三度参加した世界的な演劇察の体験から、小泉さんは自分たちを育ててくれた郷土富山の人たちにもこんな楽しさ、面白さ、喜び、感激を分かち合ってもらえないだろうかと考えるようになっていた。折から、1983年に富山県置県100年記念事業が計画されて、そこに小泉さんの提案で富山国際アマチュア演劇祭(TIATF)が企画実現される運びになった。でも、世界演劇祭に参加したことはあっても、企画・運営に関わったことのない連中ばかりで、どうやっていいものやら皆目見当がつかない。それであちらこちらから演劇祭の規則書やパンフレットなどを取り寄せて、少しずつ整理することから始めた。手探り状態ではあったが、どうやらそれなりに骨組みが出来、肉付けを始め、規則書が出来て、開催期日も昭和58年9月22日から、富山県民会館を会場として開くことになり、申込用紙等を各国宛に発送した。すべては郵便であり、電報であった。BerlinのB、SingaporeのSと電話口で大きく張り上げていた0さんの声の響きがまだ耳に残っている。
日本、アメリカ、チェコ、ハンガリー、ナイジェリア、ドイツ、イタリー、ソ連など13カ国の参加が決定して、準備の追い込みは夏休み返上で行われた。実際の裏方の仕事は膨大な量に上った。セットの作成、照明と音響の仕込み、受け入れ態勢、宿舎、食事、輸送、公演のプログラム作成、それに、コンクール形式で行うことを決めていたので審査員の選定などなど、会議を重ね、実行に移るその方面の担当は、ほとんどすべてが文芸座の皆さんであった。通訳にはヴォランティアを募ったが、富山でこうした試みが成功したのは、おそらくこれが初めてだったろう。
演劇祭まで3週間という時になって、一大事件が勃発した。アメリカからソウルに向かっていた大韓航空機がソ連の領空侵犯で撃墜されたのである。世間の雰囲気は一挙に反ソ連色に染まってしまった。しかし、富山の国際アマチュア演劇察にソ連のグループが参加して「ターニア」を公演したのであった。政治・宗教・軍事・経済は国々と人々を離反させ、相争わせることがあるが、芸術は人々を結び合わせる、とはモート・クラーク教授のモットーであるが、そのことを実感したのであった。ソ連とハンガリーとチェコのグループはナホトカから船でやってきた。いずれも海を知らない人たちだったが、折から海は荒れて、船酔いに苦しんだと開いた。撃墜事件の唯一の余波はイタリーのグループが空港の混乱で、ついに来れなくなったということだけで、結果は大成功だった。
IATAへの道
文芸座の代表小泉さんが国際アマチュア演劇連盟(IATA)の理事に選出されたのは、TIATFの1年前のことだった。日本からの代表がほとんど何もしていない、会費さえ十分に払っていないということを聞いたは、何時だったろうか。とにかく、TIATFを成功させるため、また、日本のアマチュア演劇を世界のレベルにまで引き上げるためとあって、小泉さんは理事に選出され、引き受けられた。これも、文芸座を世界に押し出す絶好の機会になった。
1984年1月中句、スウェーデンのエーレブルーという町で開催された理事会に同行したことがあった。ストックホルムで一夜の宿を取ったが、教会の鐘の音で目を覚まして、外を見ると、除雪車が出動していた。それが、先ず歩道の雪をすかして、車道の除雪を後でやっているのを見て、弱者への配慮、福祉的な考えが先行している国だなと、感じ入ったことを覚えている。エーレフルーでは「ラマンチャの男」の公演を見た。素晴らしい劇であることだけでなく、技術的には紗幕の使い方に感嘆したものであった。
理事に就任以降の小泉さんのIATAにおける活躍は世界各地域から選出されている理事たちの注目するところとなり、そこから副会長への推挽ということになったのは、当然と言えば当然ではあるが、小泉さん自身にとって、また日本のアマチュア演劇界にとって素晴らしいことであった。数次の富山国際アマチュア演劇祭の開催を重ねて、国際アマチェア演劇サミットを初めて富山で開催して、世界のアマチュア演劇が直面している問題が論じ合われた。小泉さんの行き方の特色は、世界に目を向けて視野を広げるのと同時に、自分の足下をはっきりさせ、しっかり固めていくことにあると、見受けられる。それは、アジアでのアマチュア演劇の組織作りにも窺われる。アジア地区の発展を目指すために、IATA次期会長という声が挙がっている矢先に副会長職を辞任し、IATAのアジア地区センターの組織作りに取りかかり、その代表に就くと、国際サミットを受けて、アジア・アマチュア演劇サミットの開催に取りかかった。インド、バングラディッシュ、フイリッピン、シンガポール、タイなどの東南アジア、中国、韓国、ロシア沿海州といった環日本海地区、それに加えてオーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニア地区と、文字通り西太平洋からインド洋までの区域の組織作りができあがったのは、小泉さんの大きな功績である。
海外交流の足跡
富山の文芸座とハンガリー・ハイド・ビハール県デフレツエン市のスタジオ・プレイヤーズとの交流は年と共に深まっていった。アメリカ・ニューヨーク州ヴァルハラのウエストチェスター国際演劇察の競演で批評家が言っていた両劇団による「結婚の申し込み」の帯同公演は昭和59年に北日本新聞社の100周年記念事業として富山で実現された。更に、ピンツェシュ・イシュトヴァーン氏はハンガリーの代表的劇作家の作品で面白いものがある。文芸座で舞台に乗せたらどうかと言ってきた。それが、エルケーニ・イシュトヴァーン作「ザ・トート・ファミリー」であった。英訳版が来て、その日本語版を作ることが私の仕事となったが、本当に楽しい作業であった。というのは、あらかじめ、文芸座の皆さんとなじみだったピンツェシユ氏からこの役はKさんにぴったりだし、あの役はTさんがいいだろうというサジェスチョンを受けていたから、訳出するに当たって、言い回しや、スタイルを考えるのに、大変助けになったからである。そして、昭和60年10月11,12の両日、ピンツェシュ氏の演出で富山市の教育文化会館で公演された。当時の配役はトート:谷井美夫、マリシュカ:小泉邦子、アギカ:関井早苗、郵便配達:桐島貫、少佐:角光則、優雅な少佐:平田義人、浄化槽掃除人:村井弘義、ギジ:高尾真澄、ロリンツケ:川崎昌博、その他であった。これは翌年東京でのハンガリー年に前進座の舞台で2回公演を行い、中央で惰眠をむさぼっている日本の演劇界に活を入れたものと批評された。更に、ハンガリーに凱旋興行を行い、この劇が初演されたブダペストのターリア劇場でエルケーニ夫人を招いて公演された。一杯の観客から最高の賞賛を表すスタンデイング・オヴェイションを受け、八回のカーテンコールを受けるという光栄に浴したことは、決して忘れられないとは、桐島貫氏の言葉である。ハンガリーではブダペストとデフレツエン市ほか二カ所で公演されたが、いずれも大きな反響を受けてきた。
ピンツェシュ氏が富山で、文芸座の演技陣とともに、ハンガリーのドラマを演出したのを受けて、今度は小泉さんがデフレツェンでプロ劇団「チョコナイ」の演技陣を使って公演するというハンガリー初の破天荒なイヴエントが行われた。それは日本の民話劇「夕鶴」、「三年寝太郎」と「イワンの馬鹿」(こちらの方は8ヶ月にわたるロングランだったという)であって、ハンガリー人による「夕鶴」と「三年寝太郎」は富山で凱旋公演された。こういったハンガリーとの交流に対して小泉さんは、ハンガリー建国1100年記念大統領表彰と銀メダル受賞の栄誉に輝いている。それに、IATAの国際役員としての活躍が評価されて、モナコ文化功労勲章(通称シュヴアリエ賞)が授与されている。
そして・・・
予定の枚数を遥かに超えたが、まだまだ書き留めるべきことは多く残っている。主だったところを項目的に並べると、(1)TIATFは国際青年演劇祭、国際高校演劇祭、国際こども演劇祭など、これまでに5回開催されてきていること、(2)海外公演は世界の五大陸すべてに足跡を残したこと、〈3〉富山大学の教養科目:言語表現の授業のためにイヨネスコの「授業」などを恒例として学生たちに演じて見せてきたこと、(4)レバトリーは民話劇から翻訳劇、現代劇、ミュージカルと幅が広いこと、(5)この劇団しかやっていない作品が多いこと、例えば、「ザ・トート・ファミリー」、「五月」、「グランド・ピアノ」というハンガリーの現代劇は、未だ日本で他に上演されたことを知らない。(6)富山市民演劇として、「佐々成政」、「十二の月たち」の企画に当たり、しかも劇団員がオーディションを受けて参加し、中心となって活躍していること、などこの劇団の活動のユニークさを数え上げれば枚挙にいとまがない。
一昨年(1997年)、モナコ公国のアントワーネット王女の臨席の下で、文芸座はモナコのスタジオ・ド・モナコと姉妹提携を調印している。そして、50周年記念公演として、「ザ・トート・ファミリー」が公演された。1985年から13年を経ての再演であったが、配役で変わっていたのは郵便配達:舟本幸人、ギジ:上岸泰子だけであった。ここにもこの劇団の息の長さが窺われる。年輪を重ねた文芸座の演技陣は一層劇に深みを与えているように見受けられた。
そしてもう一つの記念公演が、文芸座のこれまでなんども舞台に乗せてきた十八番、J・B・プリーストリー原作(An
Inspector Calls.)、内村直也翻案の「夜の来訪者」を更に富山弁と、関西弁と、東京弁を使って演じられたものであった。これは、利賀の新利賀山房で公演された。極めて大胆な試みであったが、それは満員の観客たちの反応にも見られたとおり大成功であった。こうした試みは、文芸座が観客を大切にしていることの現れであると、私は思う。
50周年はこの劇団にあっては一つの通過点であるに過ぎない。これから先、どんな風に進んでいくのだろうか。文芸座の未来に属目したい。
((社)富山県芸術文化協会会長)